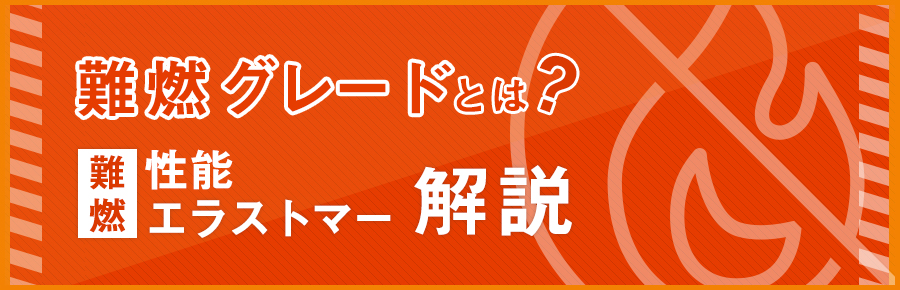
近年、製品の安全性や信頼性への要求が高まる中で、「難燃グレード」に対応した素材の選定は、多くの製造業において欠かせない要素となっています。特にUL94規格は、難燃性能を示す指標として広く認知されており、家電、医療、産業機器、自動車部品など、幅広い分野で使用されています。
しかし、柔軟性や肌触りといった機能性が求められるエラストマー系の素材では、難燃性を確保しながら製品構造に組み込むことが難しく、従来は接着やネジ止めといった手法に頼らざるを得ませんでした。
本記事では、難燃グレードの基本的な解説に加え、当社が提供する「2色成形」による難燃エラストマーとの一体化技術をご紹介します。製品設計や製造現場で直面する課題をどのように解決できるのか、その具体的なアプローチをご覧ください。
「難燃グレード」とは
難燃グレードとは、プラスチックやゴムなどの材料が「どの程度燃えにくいか」を評価するための基準です。電気・電子機器や車載部品など、火災リスクのある製品では、火源から離れても燃焼し続けないことが求められます。
代表的な難燃性評価には、米国の製品安全認証機関、アンダーライターズ ラボラトリーズ(Underwriters Laboratories:UL)による「UL94規格」があります。燃焼試験の結果に応じて5V-AからHBまでグレードが分けられています。
プラスチック試験片に既定の位置から火を当てる水平燃焼試験・垂直燃焼試験を行い、試験片の燃焼の程度からグレードを判別します。
UL94規格に基づく難燃グレード
(優) 5V-A > 5V-B > V-0 > V-1 > V-2 > HB (劣)
難燃性が高い(燃えにくい)順に、5V-A から HB までのグレードがあります。
HB は自己消化性はありませんが、遅燃性があることを示します。
5V-A ~ V-2 は自己消火性があるため熱源から離れると火が消えます。
家電製品で難燃性の材料を使用する場合、V-0 以上が望ましいとされています。
また、ABS樹脂の難燃性の基準としては V-0 / V-2 / HB が一般的に用いられています。
5V-A / 5V-B のグレードは基準が厳しく、最高レベルの難燃性能となります。
通常の用途でこのレベルが求められることは少なく、電化製品の分野ですと大型装置や情報処理装置などで用いられています。
各グレードに分類される代表的な材料
| グレード | 代表的な材料 |
|---|---|
| V-0 | PEX(架橋ポリエチレン)、RTV(室温加硫シリコンゴム)、PI(ポリイミド)、PPSU(ポリフェニルスルホン) |
| V-1 | PPO(ポリフェニレンオキサイド) |
| V-2 | PA(ポリアミド)、PC(ポリカーボネート) |
| HB | PMMA(アクリル)、PE(ポリエチレン)、PET(ポリエチレンテレフタレート) |
UL94規格の認定基準
それでは、実際にどのような試験を行って判定するのか、概要をご紹介します。
【 UL94 HB 】
試験方法:水平燃焼試験
試験片(長さ125±5mm × 幅13±0.5mm)の一方の端を固定して水平に保持し、もう片方の端に長さ20mmの炎を30秒間接炎させる。
炎を離した後も試験片が燃焼を続けた場合、燃焼速度により判定を行う。
認定基準
| 試験片の厚さ | 認定基準(燃焼速度) |
|---|---|
| 3mm以上 | 40mm/min以下 |
| 3mm未満 | 75mm/min以下 |
【 UL94 V-0/V-1/V-2 】
試験方法:垂直燃焼試験(20mm)
試験片(長さ125±5mm × 幅13.0±0.5mm)を垂直に保持し、下端に長さ20mmの炎を10秒間接炎させる。
燃焼が30秒以内に止まった場合、さらに10秒間接炎させる。
認定基準
| 認定基準 | グレード | ||
|---|---|---|---|
| V-0 | V-1 | V-2 | |
| 各試験片の燃焼時間 | 10秒以下 | 30秒以下 | 30秒以下 |
| 2回目の接炎後の赤熱時間 | 30秒以下 | 60秒以下 | 60秒以下 |
| 試験片5本の総燃焼時間 | 50秒以下 | 250秒以下 | 250秒以下 |
| 下に置いたガーゼへの火花滴下による着火 | なし | なし | あり |
| クランプ(固定器具)までの燃焼 | なし | なし | なし |
【 UL94 5V-A/5V-B 】
試験方法:垂直燃焼試験(125mm)
1)短冊試験片(長さ125±5mm × 幅13.0±0.5mm)を垂直に保持し、「下端に長さ125mmの炎を5秒間接炎させ、5秒離す」操作を5回繰り返す。
2)平板試験片(150±5mm × 150±5mm)を水平に保持し、「下方から長さ125mmの炎を5秒間接炎させ、5秒離す」操作を5回繰り返す。
認定基準
| 認定基準 | グレード | |
|---|---|---|
| 5V-A | 5V-B | |
| [短冊試験片] 5回目の接炎後の燃焼時間 | 60秒以下 | 60秒以下 |
| [短冊試験片] 下に置いたガーゼへの火花滴下による着火 | なし | なし |
| [平板試験片] 接炎後の穴の有無 | なし | あり |
難燃エラストマーとは?柔軟性と難燃性を兼ね備えた素材
難燃エラストマーとは、ゴムのような柔軟性と弾力性を持ちながら、UL94などの難燃規格に適合するように設計された高機能素材です。エラストマーにも難燃グレード V-0 ~ HB 相当の材料があります。
また、硬度は40°~90°と幅広く取り扱いがあり、柔らかい特性を生かした製品の制作も可能です。さらに、製品の仕様によっては光を透過させることもできます。
電気・電子部品、住宅設備、医療機器などで、人が直接触れる部品に使用されるケースも多く、安全性と快適性の両立が求められます。
しかし、エラストマーはその特性上、難燃剤を加えることで性能が低下したり、材料の粘性が上がることで成形性が悪化したりするなど、加工上の制約も多く存在します。さらに、難燃性を備えたエラストマーは一般的な接着剤では密着しづらく、設計・製造上の大きな課題にもなります。
当社では、これらの課題を解決する方法として「2色成形による一体化技術」を採用しています。硬質樹脂と難燃エラストマーを同時に成形することで、接着剤や後加工を不要とし、高い密着性と量産性を両立することが可能です。
2色成形による一体化技術とは?難燃エラストマーの課題を解決する手法
2色成形とは、異なる2種類の材料を1つの金型内で連続して成形し、一体化した製品を作る成形方法です。硬質樹脂と軟質エラストマーなど、性質の異なる材料を組み合わせることで、単一素材では実現できない機能やデザインを可能にします。
当社ではこの2色成形技術を活用し、難燃グレードのエラストマーと硬質樹脂の一体化を実現しています。従来、難燃エラストマーは接着剤では密着性が不十分であり、後加工による組立が必要でしたが、2色成形により接着不要・後工程不要で一体化できるようになりました。
これにより、
・部品点数の削減
・生産工程の簡略化、自動化
・外観の一体感向上
・防水、防塵性の強化
など、複数のメリットが得られます。また、設計自由度も大きく向上するため、製品の小型化・軽量化にも寄与し、コスト競争力の強化や品質安定にも繋がります。難燃性と機能性の両立が求められる製品において、2色成形は有効な解決手法です。
量産事例紹介:難燃性と2色成形の相乗効果を活かした実例
当社では、難燃グレード対応のエラストマーと2色成形技術を活かし、以下のような業界・製品への導入実績があります。
・産業機器
工場やインフラ施設で使用される制御装置の操作パネル周辺や端子部には、触感・視認性・耐久性のバランスが求められます。当社では、硬質ベース材とV-0相当の難燃エラストマーを2色成形することで、滑りにくく、操作性の高いパーツを実現。防塵性・防水性の向上と製造工程の短縮に貢献しました。
・アミューズメント部品
頻繁に触れる操作ボタンやパネル周辺部は柔らかさと安全性が必要とされるため、V-0相当のエラストマーを2色成形で一体化。耐久性と視認性を保ちながら、部品点数の削減と組立工程の簡略化に成功しました。
・携帯電話部品
難燃性能と密閉性が求められるスマートフォン周辺部において、樹脂フレームと難燃エラストマーを一体化。従来の貼り合わせ工程をなくし、製品の薄型化・軽量化を実現しました。
難燃グレードの素材を使用することは、単に「燃えにくい製品」を作るだけではありません。安全性と同時に、製造効率や製品デザイン、そしてユーザー体験を高めるためには、素材の特性に合った加工技術の選定が鍵を握ります。
当社の2色成形技術は、難燃エラストマーの課題を解決し、部品一体化による高付加価値な製品づくりを支援します。「接着が難しい」「安全性と機能性を両立したい」といった課題をお持ちの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

